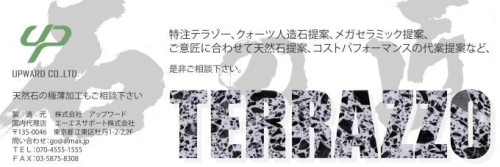新着情報(最新消息)
2024-10-15 11:50:00
在垂钓平台,许多游客分散到各个钓点,或挂饵抛竿或手握钓竿等鱼上钩,游客悠闲而放松,尽享垂钓魅力。

据垂钓中心相关负责人透露,今年国庆假期期间的垂钓人数较去年同期增长了20%,所有水上垂钓民宿在国庆节前就已全部预订一空。为了迎接国庆节的到来,垂钓中心在节前做了大量的准备工作。为确保游客们有足够的垂钓资源,垂钓中心节前就增添了多个垂钓点,并提前投放了2万条鱼苗至水中,后续也会根据游客垂钓情况持续补充鱼苗。同时,垂钓中心还对软硬件设施进行了维修和更新,力求为游客提供更佳的服务和体验。


2024-10-15 11:49:00
🔳正社員・パート
勤務地:東京都江東区 (東陽町、門前仲町、テレワーク)
給与:20~35万(年齢・能力に応じる)
時間:相談
🔳仕事内容:
1. 建材貿易
2. ブラント品販売
3. ネットショップ新規開設
🔳応募資格&条件
· パソコンやインターネットに強い方、学生可、ビザ発給可
· 必須:2ヵ国語(日本語+中国語)
· 優遇:ネットショップ運営経験、楽天などオープンマーケット運営経験者
🔳募集について
職種名:
1. 貿易業務助手
(要求:パソコン堪能、CAD 解読必須、英語ビジネスレベル可)
2. ホームページ維持員(要求:パソコン技能)
3. ライブ販売員、ネットショップ運営マネージャー
(要求:健康、向上、形象佳)
🔳お問い合わせ先:
株式会社アップワード
E-mail:
2024-10-15 11:49:00
(本报讯)地处江西庐山西海风景名胜区的易家河村,是个典型的山区农村。该村三面环山,一面临水,是一个集温泉养生度假、生态旅游休闲为一体的柑橘之乡、明尚书魏源故里。全村以柑橘为主导产业,柑橘种植总面积4600余亩,总产量4200万斤,产值8000余万元。旅游为该村支柱产业,近十余年的发展,基本形成了一湖水、一桌饭、一棵树、一条溪、一口泉的产业发展态势。如今的易家河村已然成为了民风淳朴、治理有效、生活富裕、生态宜居美丽乡村。






 (橘子形状不同,甜度不一)
(橘子形状不同,甜度不一)

以上就是小编为您分享《江西这个村,主导产业是柑橘!年产值8000余万元》的全部内容,更
2024-10-15 11:46:00
(本报讯)10月15日,来自世界五大洲18个国家和地区的20余位海外华文媒体高层及骨干记者、编辑走进江西九江庐山西海风景名胜区,体会湖光山色中的浪漫与休闲。庐山西海风景名胜区位于江西省北部、九江市西南部,是一处集国家级风景名胜区、国家5A级旅游景区、国家水利风景区、国家森林公园、中国中小学生研学实践教育基地、中国国家体育旅游示范基地、中国体育旅游精品景区、中国十佳生态旅游示范景区、中国最佳旅游胜地等为一体的山岳湖泊型特大景区。






2024-10-15 10:38:00
“烟雨朦胧中的庐山西海,让人流连忘返。”10月15日,站在高99米的江西庐山西海风景名胜区西海之星玻璃观光塔上,俯瞰庐山西海碧波荡漾,柬埔寨《柬华日报》副总编辑杜冰玉忍不住发出感叹。
(图为采访团一行在西海之星玻璃观光塔上,俯瞰庐山西海碧波荡漾。刘占昆 摄)
当天,2024海外华文媒体江西行采访团走进庐山西海风景名胜区,来自世界五大洲18个国家和地区的20余位海外华文媒体高层及骨干记者、编辑零距离体会湖光山色中的浪漫与休闲。
庐山西海风景名胜区位于江西九江西南部,水域面积308平方公里,是一处山岳湖泊型特大景区。湖面碧波万顷,湖中千岛落珠,岛屿间被形态各异的桥梁串成一幅“东方美学图”。
当天,2024海外华文媒体江西行采访团走进庐山西海风景名胜区,来自世界五大洲18个国家和地区的20余位海外华文媒体高层及骨干记者、编辑零距离体会湖光山色中的浪漫与休闲。
庐山西海风景名胜区位于江西九江西南部,水域面积308平方公里,是一处山岳湖泊型特大景区。湖面碧波万顷,湖中千岛落珠,岛屿间被形态各异的桥梁串成一幅“东方美学图”。


(图为采访团一行在西海之星玻璃观光塔上,俯瞰庐山西海碧波荡漾。刘力鑫 摄)
乘船进岛,采访团一行亲身感受“水天相映成一色,人船穿游翡翠里”的美妙意境。站在船头远望,庐山西海周边的山林笼罩在云雾中,犹如一幅水墨画,缥缈淡雅。
在西海之星玻璃观光塔的电梯门口徘徊许久,恐高的杜冰玉还是鼓起勇气踏入观景台。“满眼美景让我克服了恐惧。”她说,其将持续报道庐山西海,让柬埔寨民众知道中国有个这么美的地方。
近年来,随着社会经济发展及生活水平提高,民众日益重视生活品质和体验,越来越多的年轻人选择假期走出城市放松身心,户外、自然类旅游活动需求不断上升。
江西庐山西海国资旅游发展有限公司岛屿管理部主管陈国清说,庐山西海自然资源丰富,拥有一类水质、一级空气和独特岛屿,交通便利且地处旅游热区,发展旅游业有“好牌”。
立足资源禀赋,除大力发展游湖登岛等传统旅游观光外,庐山西海风景名胜区还做靓“旅游+”文章,体旅融合、文旅融合、农旅融合等新业态“异军突起”,解锁了柑橘采摘、垂钓休闲等一批新产品和新体验。
乘船进岛,采访团一行亲身感受“水天相映成一色,人船穿游翡翠里”的美妙意境。站在船头远望,庐山西海周边的山林笼罩在云雾中,犹如一幅水墨画,缥缈淡雅。
在西海之星玻璃观光塔的电梯门口徘徊许久,恐高的杜冰玉还是鼓起勇气踏入观景台。“满眼美景让我克服了恐惧。”她说,其将持续报道庐山西海,让柬埔寨民众知道中国有个这么美的地方。
近年来,随着社会经济发展及生活水平提高,民众日益重视生活品质和体验,越来越多的年轻人选择假期走出城市放松身心,户外、自然类旅游活动需求不断上升。
江西庐山西海国资旅游发展有限公司岛屿管理部主管陈国清说,庐山西海自然资源丰富,拥有一类水质、一级空气和独特岛屿,交通便利且地处旅游热区,发展旅游业有“好牌”。
立足资源禀赋,除大力发展游湖登岛等传统旅游观光外,庐山西海风景名胜区还做靓“旅游+”文章,体旅融合、文旅融合、农旅融合等新业态“异军突起”,解锁了柑橘采摘、垂钓休闲等一批新产品和新体验。

(图为当地村民采摘柑橘。(资料图)庐山西海风景名胜区 供图)
金秋十月,来庐山西海风景名胜区柘林镇易家河村采摘柑橘的游客纷至沓来。“围绕打造万亩柑橘产业园,我们建设柑橘分拣、冷藏和产业加工中心,不断扩展柑橘深加工产业链,推动旅游基础设施升级。”易家河村党委书记陈全民说。
“庐山西海很浪漫,来到这里,心情愉悦、身心放松。”菲律宾《商报》执行总编蔡友铭说,庐山西海的空气负氧离子含量高,很适合发展健康养生旅游。相信通过海外华文媒体的宣传,会有更多海外华侨华人了解和爱上庐山西海。
在蔡友铭看来,生态是庐山西海旅游产业蓬勃发展的基础,要充分发挥当地山水秀美的优势,推出形式多样的精品旅游线路。(完)
金秋十月,来庐山西海风景名胜区柘林镇易家河村采摘柑橘的游客纷至沓来。“围绕打造万亩柑橘产业园,我们建设柑橘分拣、冷藏和产业加工中心,不断扩展柑橘深加工产业链,推动旅游基础设施升级。”易家河村党委书记陈全民说。
“庐山西海很浪漫,来到这里,心情愉悦、身心放松。”菲律宾《商报》执行总编蔡友铭说,庐山西海的空气负氧离子含量高,很适合发展健康养生旅游。相信通过海外华文媒体的宣传,会有更多海外华侨华人了解和爱上庐山西海。
在蔡友铭看来,生态是庐山西海旅游产业蓬勃发展的基础,要充分发挥当地山水秀美的优势,推出形式多样的精品旅游线路。(完)