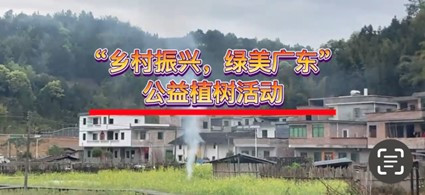新着情報(最新消息)
植树添绿!种下紫花风铃木赴春光
早春の3月は、緑が芽吹くシーズンだ。3月12日、広州市从化区呂田鎮三村村で、“郷村振興、緑が美しい広東”と銘打った公益植樹活動が、予定通り行われた。春風を背に受けながら、人々は共にシャベルやバケツなどの道具を手に取り、バケツの水を持って走り回りながら木を植える場所に水をかけ、手足で苗を建てて根を固定し、さらには腰をかがめて鋤を振るいながら土寄せを行った。全ての人の息が合った働きにより、200株のパウダルコの苗木が力強くまっすぐに立ち、広い大地に一筋の緑を添えた。
早春三月,绿意萌动。3月12日,在广州市从化区吕田镇三村村,一场名为“乡村振兴 绿美广东”的公益植树活动如期而至。
伴着几缕春风,众人齐齐拿起铲子、水桶等工具,或是来回跑动提水浇坑,或是手脚并用扶苗定根,弯下腰挥锹培土。
经过大家的默契配合,200棵紫花风铃木的树苗已勃然挺立,为大地增添了一片绿意。
畅游魔术之旅! 东莞市文化馆魔术节目“奇迹”迭出
燃え盛る炎の下で幕が下り、子どもたちは瞬間的に見事な腕前の魔術師に変身する…。数日前、(プロの魔術師である)張得恩氏の「個人大型魔術興業」が東莞市文化館のスターシアターで開催された。演目である<妙趣横生(優れた趣が溢れる)>の中では、魔術師が観客の願いを実現し、人々を度々驚かせ、神秘的なアヒルのトリックで好奇心に火をつける。そして驚きと奇抜さ、眩さに満ち溢れ、変幻自在で、神秘的なその色彩感が、観客らも一体感を感じられるイマーシブな魔術の宴を体験させてくれるのだ。今回の公演は東莞市の青年芸術家による、夢実現に向けたアクションプログラムの一つで、優れた芸術的才能を有する青年芸術人材を発掘するための取組でもある。
火中“燃烧”的幕布褪下、小朋友瞬间变成技艺精湛的魔术师……日前,张得恩个人大型魔术专场在东莞市文化馆星剧场举行。
在节目《妙趣横生》中,魔术师为观众实现愿望,让人惊喜连连,神奇的“鸭子戏法”点燃了观众的好奇心,“惊、奇、炫、幻”的魔幻色彩,让观众沉浸式感受了一场魔术盛宴。
本场演出是东莞市青年艺术家圆梦行动活动之一,致力于挖掘一大批具有优秀艺术才能的青年艺术人才。
广州越秀公园:红墙城下木棉艳
広州市の越秀公園は、都市の大動脈の中に息づくオアシスである。越秀公園には歴史上、粤秀山や越王山、観音山等の美しい異名が冠せられてきた。園内には群れになって咲く木綿(キワタ)の花が根を張り、この内9株は名だたる老木である。春になると観音山では、俗に「英雄花」とも呼ばれる木綿が競うように咲き誇り、枝の先端を伸ばして、辺りは蕾であふれかえる。中山記念碑の周りは、まるで多くの木綿に守られているかのようだ。深紅の木綿に囲まれながら、先人たちの革命精神は未来永劫、受け継がれていくであろう。
广州市越秀公园,城市主动脉中的绿洲。越秀公园历史上又有粤秀山、越王山、观音山的美名。
园内有一批木棉在此扎根,其中有9株为古树名木。春日之时,观音山上英雄花木棉竞相绽放,枝头延展,挂满花蕾。
而在中山纪念碑周围,亦有多株木棉守护着。鲜红木棉簇拥,先辈革命精神生生不息地延续。
汕头陈慈黉故居:黉院惠风 锦瑟年华
タイ華僑である陳慈黌氏の旧居は広東省汕頭市澄海区前美村にあり、嶺南エリアで最大規模の完全な保存状態で残る華僑住宅で、“嶺南一の華僑住宅”という誉れ高い異名をもつ。旧居の中に入ると、潮州の「金漆木彫」や「石彫」、嵌瓷画、油絵など潮汕地区の多様な伝統工芸品が至る所に見られ、敷地内にある別々の中庭を行き交うと、全ての庭と部屋にそれぞれ味わいや特色があり、床のタイル一つとっても完全に同一ではなく、歩を進めるごとに景色が変わり、まさに独特な別天地の雰囲気を醸し出している。近年、一連の修繕とリノベーションを経て、陳慈黌旧居はすでに潮汕エリアを旅行する観光客が最もお気に入りの遊覧スポットの一つとなっており、同時に汕頭市が売り込みに全力を注ぐ華僑ブランドの象徴でもある。
陈慈黉故居,位于汕头市澄海区前美村,是岭南地区规模最大、保存最完整的侨宅,有“岭南第一侨宅”美称。
走进陈慈黉故居,潮汕金漆木雕、石雕、嵌瓷、彩绘……多种潮汕传统工艺随处可见,穿梭于不同庭院中,每间院子与房间各具韵味与特色,地砖的样式也不尽相同,移步换景,独具洞天的风格在此体现。
近年来,经过一系列修缮活化,陈慈黉故居已成为许多游客潮汕之旅中最喜爱的游览景点之一,也是汕头市全力打造侨品牌的一处缩影。
打造“粤海粮仓”! 广东培育万亿级现代化海洋牧场产业集群
“徳海1号”、“海威1号”、“ 澎湖号”など、現在広東省は現代化された海洋牧場の建設を加速させており、兆単位(人民元)レベルの市場規模を持つ産業クラスターの育成に力を入れている。潮州市の饒平県で目下建設中の現代化海洋牧場の第1号プロジェクト、“岸上花鱸良種場”(岸上のスズキ優良種養殖場)が完成したあかつきには、良質なスズキ稚魚の年間養殖量が3億匹に達し、これに伴い広東省はスズキ養殖稚魚の海外依存から根本的に脱却することが可能となる。広東省では現代化された海洋牧場と発展モデル、そしてバイオテクノロジーを積極的に結びつけ、海洋保健食品や化粧品、生物医薬(バイオメディカル)等の領域に幅広く応用して、新たな成長分野を打ち立てようと模索しており、これはいわば一匹の魚から、多数の魚に相当する価値を生み出す取組と言える。
“德海1号”、“海威1号”、“澎湖号”……当前,广东正加快推进现代化海洋牧场建设,着力培育万亿级现代化海洋牧场产业集群。
在潮州市饶平县,目前正加快建设的现代化海洋牧场第一批项目“岸上花鲈良种场”,建成后年培育优质花鲈鱼苗可达3亿尾,可让广东彻底摆脱花鲈养殖种苗对外依赖。
广东积极探索“现代化海洋牧场+”发展模式,并与生物科技结合,在海洋保健食品、化妆品、生物医药等领域广泛应用打造新的增长点,让“一条鱼”产生“多条鱼”价值。