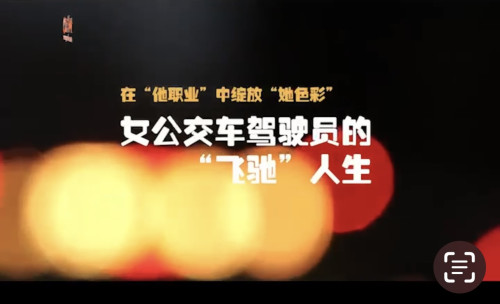新着情報(最新消息)
昨年5月1日時点で日本国内の大学・大学院、専門学校、日本語教育機関等の教育機関に在籍していた外国人留学生の総数が、前年比で約1万1千人減り23万1146人だったことが分かった。新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、留学生数は2019年の約31万2千人をピークに減少へと転じており、2022年で4年連続の対前年比マイナスとなった。日本学生支援機構(JASSO)の調査によるもの。
JASSOのまとめによれば、留学生の在学段階別では高等教育機関で、大学(学部)7万2047人、大学院5万3122人、短期大学1863人、高等専門学校480人、専修学校(専門課程)が5万1955人などとなっていて、対前年比では大学院のみが微増だったが、専修学校(専門課程)はマイナス26%と大幅に減った。一方、日本語教育機関は前年(4万567人)より2割(約9千人)ほど持ち直し、4万9405人だった。調査直前の昨年3月より、日本政府が水際緩和に踏み切り、入学予定者の入国が再開されたことが作用したとみられる。
留学生の出身国・地域別では中国(10万3882人)、ベトナム(3万7405人)、ネパール(2万4257人)、韓国(1万3701人)、インドネシア(5763人)、台湾(5015人)等が多い。中国出身者の全留学生に占める比率が45%と極めて高くなっている。また主要国中、ネパールが対前年比28%増と唯一大きな伸びを示した。
留学生の専攻分野別では、人文科学が8万291人と最多で、前年度一番多かった社会科学(6万3096人)を逆転した。このほか、工学(3万7487人)、保健(5829人)、理学(4361人)、農学(4200人)の順となっている。
都道府県別(学校所在地)の在籍留学生数では、東京都(7万8957人)を筆頭に、大阪府(2万1190人)、福岡県(1万5955人)、京都府(1万4205人)、兵庫県(1万633人)、愛知県(1万122人)の1都2府3県が、1万人以上を擁する。首都圏では東京都のほか、埼玉県(8951人)、千葉県(7280人)、神奈川県(6246人)も相当数に上る。
※留学生受入れ数の多い大学は?
日本学生支援機構(JASSO)の調査では、主要大学に在籍する留学生の数も明らかになった。2022年5月1日時点で、全国最多の留学生を受入れているのは東京大学で4397人だった。数が多い上位10校中、国立大学が京都大学(2564人)、大阪大学(2514人)、九州大学(2359人)、筑波大学(2189人)、東北大学(2074人)を含めて6校を占める。
私立大学で総数10傑入りしているのは、早稲田大学(4208人)、立命館大学(2698人)、日本経済大学(2599人)、立命館アジア太平洋大学(2392人)の4大学。このほか、千名を超えている私大が慶應義塾大学、日本大学、東洋大学、東海大学、京都情報大学院大学、明治大学など14大学に上る。
※来年度以降の在籍数は増加に転じる見通し
なお本調査が行われたのは昨年5月であり、この後、政府の段階的な水際緩和により、留学生の新規入国者数は大幅に回復している。出入国在留管理庁によれば、2022年中に『留学』の在留資格を取得し新規で来日した外国人の数は16万7128人と、史上最高の数となった。コロナ禍で低迷してきた各教育機関の在籍留学生数は、2023年度以降、再び増勢に転じる可能性が高いとみられる。
**************************************
日本学生支援機構(JASSO)が実施した外国人留学生の在籍状況調査(2022年度)において、全国の日本語教育機関に在籍する留学生は昨年5月1日時点で4万9405人と5万人に迫り、前年度との比較では22%(8838人)回復しているが、その具体的な内訳も明らかになった。
出身国・地域別では、最多の中国が1万8120人で全体に占める割合は37%となり、これに昨今急増中のネパールが1万500人で肉薄し、ベトナムが8557人で続く構図だ。主要3か国以外では、スリランカ(1467人)、ミャンマー(1139人)、インドネシア(1054人)、モンゴル(959人)、バングラデシュ(946人)、台湾(767人)、ウズベキスタン(655人)等となっている。
日本語教育機関留学生の分布を都道府県(学校所在地)別にみると、東京都(2万1479人)を筆頭に、大阪府(5109人)、福岡県(3651人)、愛知県(2774人)、兵庫県(2266人)、京都府(2076人)までが2千人以上。このほか、埼玉県(1796人)、千葉県(1350人)、静岡県(1314人)、神奈川県(1125人)も多い。
日本語教育機関留学生の宿舎状況では、民間宿舎・アパート等が6割(2万9649人)と多数を占めるが、公的宿舎に住む留学生も4割に達しており、中でも学校が設置する留学生宿舎の居住者が全体の37%(1万8476人)で、この比率は大学等の高等教育機関(12%)より相当高い水準となっている。なお大学等高等教育機関の場合は、民間宿舎・アパート等の居住者が84%を占める。
(関連記事 『留学生新聞ニュース』2023.3.7号)
★昨年5月時点の留学生数、1万1千人減の23万1千人
昨年5月1日時点で日本国内の大学・大学院、専門学校、日本語教育機関等の教育機関に在籍していた外国人留学生の総数が、前年比で約1万1千人減り23万1146人だったことが分かった。新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、留学生数は2019年の約31万2千人をピークに減少へと転じており、2022年で4年連続の対前年比マイナスとなった。日本学生支援機構(JASSO)の調査によるもの。
JASSOのまとめによれば、留学生の在学段階別では高等教育機関で、大学(学部)7万2047人、大学院5万3122人、短期大学1863人、高等専門学校480人、専修学校(専門課程)が5万1955人などとなっていて、対前年比では大学院のみが微増だったが、専修学校(専門課程)はマイナス26%と大幅に減った。一方、日本語教育機関は前年(4万567人)より2割(約9千人)ほど持ち直し、4万9405人だった。調査直前の昨年3月より、日本政府が水際緩和に踏み切り、入学予定者の入国が再開されたことが作用したとみられる。
留学生の出身国・地域別では中国(10万3882人)、ベトナム(3万7405人)、ネパール(2万4257人)、韓国(1万3701人)、インドネシア(5763人)、台湾(5015人)等が多い。中国出身者の全留学生に占める比率が45%と極めて高くなっている。また主要国中、ネパールが対前年比28%増と唯一大きな伸びを示した。
留学生の専攻分野別では、人文科学が8万291人と最多で、前年度一番多かった社会科学(6万3096人)を逆転した。このほか、工学(3万7487人)、保健(5829人)、理学(4361人)、農学(4200人)の順となっている。
都道府県別(学校所在地)の在籍留学生数では、東京都(7万8957人)を筆頭に、大阪府(2万1190人)、福岡県(1万5955人)、京都府(1万4205人)、兵庫県(1万633人)、愛知県(1万122人)の1都2府3県が、1万人以上を擁する。首都圏では東京都のほか、埼玉県(8951人)、千葉県(7280人)、神奈川県(6246人)も相当数に上る。
※留学生受入れ数の多い大学は?
日本学生支援機構(JASSO)の調査では、主要大学に在籍する留学生の数も明らかになった。2022年5月1日時点で、全国最多の留学生を受入れているのは東京大学で4397人だった。数が多い上位10校中、国立大学が京都大学(2564人)、大阪大学(2514人)、九州大学(2359人)、筑波大学(2189人)、東北大学(2074人)を含めて6校を占める。
私立大学で総数10傑入りしているのは、早稲田大学(4208人)、立命館大学(2698人)、日本経済大学(2599人)、立命館アジア太平洋大学(2392人)の4大学。このほか、千名を超えている私大が慶應義塾大学、日本大学、東洋大学、東海大学、京都情報大学院大学、明治大学など14大学に上る。
※来年度以降の在籍数は増加に転じる見通し
なお本調査が行われたのは昨年5月であり、この後、政府の段階的な水際緩和により、留学生の新規入国者数は大幅に回復している。出入国在留管理庁によれば、2022年中に『留学』の在留資格を取得し新規で来日した外国人の数は16万7128人と、史上最高の数となった。コロナ禍で低迷してきた各教育機関の在籍留学生数は、2023年度以降、再び増勢に転じる可能性が高いとみられる。
*****************************************
女公交车驾驶员的“飞驰”人生
男女の間には生まれつきの違いがあることは否定できず、この差異は時として職業においてさらに鮮明に表れる。 「彼の職業」なるものがあるとすれば、その職業は一般的に男性向きとみなされており、この職業に就く人の性別は男性単独か、あるいは男女の比率がかけ離れていることを意味する。3月8日の国際女性デーの到来に際し、私たちは俗に「彼の職業」と言われる職種の中に、煌めきを見せる「彼女」の姿を見出そうと試みた。動画から、「彼女らのストーリー」を見てみよう!
不可否认,男女天生有差异,这种差异到了职业当中,有时会更明显,因而生出一些“他职业”:某种职业常被认为更适合男性,该职业性别单一或男女比例悬殊。
在“三八”国际妇女节来临之际,我们尝试在“他职业”中寻找“她色彩”。
戳视频,一起来看看她们的故事。
26年四度牵手,广州与“梅花奖”情缘再续
数日前、第9回中国演劇賞・梅花公演賞(第31回中国演劇梅花賞)が広州で正式に幕を開けた。今回の梅花賞のフィナーレを飾る最終審査では、全国各地の演劇から特に選りすぐりのものを集中的に公開し、優秀な演劇俳優と演劇作品を選出する。多くの観客たちと広州、香港、マカオの市民はさらに今年5月、新たな“梅花”の満開期となる、豪華絢爛な演劇芸術フェスティバルを迎える。すでに2017年の時点で、中国演劇家協会の崔偉秘書長はインタビューで、広州の観客を片時も忘れたことはないとして、「広州は演劇への理解が深い(演劇に通じた)都市である」と語っていた。
日前,第九届中国戏剧奖·梅花表演奖(第31届中国戏剧梅花奖)在广州正式启动。
据悉,本届梅花奖终评活动将集中展示全国各地各剧种精粹,推出优秀戏剧演员和戏剧佳作。广大观众和广州、香港、澳门市民将在今年5月迎来新一轮“梅花”绽放、精彩纷呈的戏剧艺术盛宴。
早在2017年,中国戏剧家协会秘书长崔伟在接受采访时就表示,广州观众让他念念不忘:“广州是戏剧知音的城市。”
日啖樱花三百朵!靓丽樱花原来不止可观
最近、「漢風古韻(昔の風格を持つ中華風)」をテーマとする桜祭りが、広州市番禺区の宝墨園で開幕した。宝墨園は湖に面して軒や榭が建てられ、遊覧や休息のために設けられた楼閣の中には数百本の広州桜が植樹されていて、満開の時期には、靄が立ち込めるような雰囲気の下、ピンク色の花々が芳ばしく、観光客が思い思いにレンズを向ければ、まるで個性溢れる国産の花見作品のような趣を呈する。また桜は単に鑑賞を楽しむだけに止まらず、見る者をうっとりさせ魅了してやまない。観光客のニーズに応えようと、宝墨園では高価な桜ケーキや桜アイスクリーム、さらには「錦の上に花を添える」が如く、ブローチ、ペンダント、桜をモチーフにした古風なうちわや扇子など、オリジナルの文化・クリエイティブグッズを発売しており、文化とオリジナリティのイメージを通じて、都市の魅力を表現しようと試みている。
近日,汉风古韵主题樱花节在广州市番禺区宝墨园开幕。
宝墨园在临湖轩榭、亭台楼阁中广植了数百棵广州樱,盛开时烟波浩渺、红粉芳菲,游客随手一拍就是别具一格的国潮赏樱大片。
而且,樱花不止于赏,更能秀色可餐。为满足游客需求,宝墨园推出高颜值的樱花蛋糕、樱花雪糕、“锦上添花”胸针、吊坠、樱花主题古风团扇、折扇等系列樱花主题文创品,通过文化与创意的演绎,展现更多的城市魅力。